法律コラム
無題
ここのところ、スムーズに進まない案件が多くて、いささか困っています。ただ、自分の力でどうこうできる部分はとても限られているので、こつこつやるよりほかありません。
思い通りにならなかったり、不運が重なることは日常茶飯事ですが、そこをどう処していけるのか、そこで真価を問われている気がします。
こんな私でも、困難な経験から、あるいは書物から、そうした時の対処方法について色々と学びました。今回は、そうした話をしたいと思います。内容的には矛盾しますが、2つほど。
1つは、たとえゆっくりとではあれ、決して足を止めてはならないということです。足を止めたら、固まって動けなくなってしまうかも知れない。音楽が鳴っているうちはステップを踏み続ける。そうすれば少しづつでも物事を動かしていくことができるし、それが結果として改善に繋がるかも知れない。少なくとも、何とか前を向くよすがにはなる。
もう1つは、つらい時には足を止め、ゆっくりと休んで、たっぷりと水を飲んでもいいんだということです。他人からどう見えようと、ゆっくり休んで自分で自分を大切にしてやる。それで力が戻って、また歩こうという気持ちになれたら、またゆっくりと歩き出せばいい。限界まで無理をすると、回復するまで余計に時間がかかりますし、場合によっては自分を壊してしまいかねません。スポーツの怪我と同じように。
そんな風に考えるようになったのも、それなりに歳を取ってきたからかも知れません。若い時は、もっと性急で、もっとはっきりした、もっと強気で生硬な価値観で生きていたような気がします。でも、色んな経験をして、それではもたないと自分で分かってきたわけです。
仕事柄、傷ついている人を見ることが多々あります。心を病んでしまっている人も少なくありません。特に若い人たち。とても気の毒だし、何とかしてあげたいとも思います。でも、我々に出来ることなんて限られています。彼ら彼女らに必要なのは、一過性のサポートではなくて、より息の長い人生の指針のようなものです。それは頭で理解するものではなく、身に染みてスッと体に入るものでなくてはならないし、他者からもたらされるようなものではありません。自ら掴み取る必要のあるものです。
他方で、傷ついている時には、余り性急にそれを癒やそうとしないことも場合によっては必要だと感じています。結局のところ、時間にしか癒やせない傷がある。自分で努力しても、他人が働きかけても、しかるべき時間をかけなければ乗り越えられない物事がある。少しずつ受け容れ、ゆっくり整理し、しかるべきところに何とか納め、そうして乗り越えていく必要があります。それは、その時にはとても辛いことです。苦しみが永遠に続くのではないかとも感じます。でも、きっと何時かは乗り越えられるのだと信じて、ぐっと我慢するしか方法はありません。それを抱えて日々を何とか過ごしていく。そして、ある時、ふと何とか乗り越えられたことに気づきます。そして人生の景色が少し変化したことにも気づきます。
答えはありませんが、そうして生きていくしかないんでしょうね。
当たり前だけど個人的に不思議な話
当たり前の話をするなと怒られるかも知れませんが、ご容赦下さい。
少し前に母が亡くなり、父も施設で生活するようになりました。そうすると色々考えさせられます。
親が亡くなって改めて思うことは、やはり人は何時かは死んでしまうし、その人が抱えていた色んな気持ち、とても強い思いであっても、結局は雲散霧消してしまうということです。そうなのであれば、色々と葛藤し、思い悩んで生きていることに、結局のところ意味はないのかという思いにも駆られます。
でも、きっとそうではないですよね。私が感じるのは、諦めて無気力に希望なく過ごすよりも、結局は消えてしまうとはいえ、前向きに楽しんで努力して生きること、そのためにもがくことこそ、生きている意味を与えてくれる原動力である(本来的には意味はなくても、意味を付与する契機である)ということです。まあ、平たく言うと、不幸で生きるよりも幸福に生きたいということですね。当たり前のことです。
そして、そのためには、誰かを強く求め、誰かに強く求められること、そうしたことがやはり重要だろうと感じます。男女であっても、親子であっても、別の形であっても、どんな形であっても。村上春樹の小説に繰り返し繰り返し描かれているように。これも当たり前のことです。
ただ、私が不思議なのは、何故そうなのかということです。どうして、そんなことが、それほどの意味を持つのか(あるいは持つように思われるのか)ということです。
専門外でよく分かりませんが、生物の中でも、そんなことに大きな意味がありそうなのは人間だけのような気がします。「生殖」という観点を少し離れて、それほどの強い思い、多様で複雑な思いを持って、他の個体に相対しているのは人間だけのような気がするのです。それが何とも不思議です。答えのない問いで、誠に申し訳ないのですが。
それは良い意味でも悪い意味でも現れます。「憎悪」といった感情も、同じ根っこから生えており、良い面と悪い面は表裏一体で、その時々によって姿を変えてくるといった印象です。
人と人とが強く求め合って結びついても、何らかのきっかけで上手くいかなくなり、その関係が破綻してしまう。誰よりも強く求めていた人を、最も忌み嫌うようになってしまう。
それもまた往々にして起こりうることです。残念ではありますが、誰が悪いといった問題でもなく。優劣、善悪も関係なく。
我々弁護士は、そうした実例を日常的に目にすることになります。なかなか熾烈なことも少なくありません。
ここを乗り越えて、また別の形でやり直して欲しいなと感じています。
Happiness Has Your Name
最近偶然手に入れたイタリア・ジャズのアルバム(CD)のタイトルですが、素敵な題だと思いませんか。リーダーはピアニストのRomano Mussolini、そう、あのムッソリーニの息子さんです。すごく良い盤です。
時間がないので一筆書き
今月は、このコラムに何を書くか本当に何も考えておらず、困ったなと通勤の車内で何を書こうかツラツラと考えておりました。でも、何も書く内容を思いつきません。そのため、今月も雑感的なことでお茶を濁させて頂きます。
先日、裁判所の待合室で依頼者さんと雑談していた際、出身高校の話になり、高校生のころのことを少し思い出しました。そして、ありきたりですが、随分と時が経ったと改めて実感しました。赤ちゃんのころから知っている甥や姪も、最近結婚して家庭を持っており、息子も成人して今は大学生です。母はもうなく、父も施設で生活するようになりました。
そんなこんなで、自分も世代の連鎖の一部なのだなと感じることが最近は多くなりました。
ただ、そうすると、上の世代から引き継いでおくべきこと、知っておくべきことが何だか気になってきます。
うちの実家は昔ながらの家というか、あまり子どもと父とが親しく話すことのない家でした。結婚して独立してからも、私は、姉のように孫を連れて実家に頻繁に顔を出すこともなかったので、そんなに父とは話す機会もありませんでした。でも、母が施設に入り、父が一人暮らしになってからは、近くにいたのが私だけだったこともあって、2週間に一回は実家まで出向いて、色々と用事を片付けるようになりました。父も最初は「来んでいい」「早く帰れ」という態度でしたが、次第に「あれやってくれ」「ここに連れて行ってくれ」「これ買ってきてくれ」と私を頼るようになりました。そんな折りに、私はポツポツとではありますが、父から父自身の話や、親せきの話、祖父・曾祖父の話を聞くようになりました。初めて知る話も多く、おかげで、それまでより父という人間をよく理解できるようになりました。そんな風に感じて生きていたんだと。また、父は、色々な事を私に引き継ごうとするようになりました。実家のこと、お墓のこと、親せきのこと。私がこういう仕事に就いたこともあったのだと思います。実家通いをしている時は正直少し面倒でしたが(同じ市内とはいえ結構遠いので)、今となっては行っておいて良かったなと感じています。すごく貴重な、得がたい機会でした。
こうして上の世代から引き継ぐべきものは、ある程度は引き継げた。そして、下の世代(息子)に引き継がなくてはなりませんが、それはまだ先のこと。
私たちは、否応なく年を取り、いつかこの世を離れていく。そのようにして世代は常に移り変わの、社会も価値観もどんどん変容する。
JAZZの古いスタンダードナンバーに「Fly me to the moon」という、とても有名な曲があります。ある著名なアニメ作品で用いられたことで、日本でもよく知られるようになりました。この曲は、歌詞の一部を取って元々は「In Other Words」という題名だったと記憶しています。女の子が彼氏に「月に連れて行って」とか色々と言うのは、言葉を換えれば、「手を繋いで」とか「キスして」とか「愛してる」ということなんだよという、そんな内容の曲です。そんな風にして、人は誰かと結びつき、順々に世代は移り変わっていく。
でも、いつの世も、同じように人が人を強く求めるというのは、当たり前のことではあるのですが、何とも不思議なことですね。
また一年が終わろうとしている。
早いもので、今年も残すところあと10日ちょっとになりました。
「何とか今年も無事に乗り切れた」。毎年この時期になると同じ感慨を抱きます。そして、来年も同じように無事に年の瀬を迎えられるようにと願います。
「隣の芝生は青い」というか、誰しも他人と比べていささか暗澹たる思いになることがあると思います。私もそうです。同じところからスタートして随分と違った人生になってしまったものだなとか。ただ、隣の芝生もきっと青くはないでしょうし、悩みの種類が違うだけできっと似たり寄ったりだろうと感じています。偶々、(幸運にも)同じスタートに立てていただけで、そもそもの出来が違うので比べても仕方ないよなとも感じます。結局のところ、あるがままの自分の人生を生きるしかありません。
そんなとき、パッとしなかった幼かったころの自分が頭に浮かびます。(特に)小学生のころは、自分で言うのも何ですが、本当にパッとしなかった。「きっと自分の人生なんて、そんな大したものじゃないだろうな。嫌な目にたくさん遭うんだろうな」などと、若いくせに変に人生を悲観していました。そんな自分を思い起こすと、「まあ、俺にしてはよくやったよ」と思います。人生は考えていたほど悪くはなかったし、自分にしてはなかなかに上出来だ。誇れるほどのことは何もありませんが、それなりにベストは尽くしてきた。そのことに自分なりに満足しています。それはある意味とても幸福なことです。
ありきたりですが、年の瀬になるとクラシックが聴きたくなります。10数年前に1年間ほど浴びるようにクラシックを聴いたことがありました。でも、あまりのめり込めず、今では折に触れて聴く程度になってしまいました。それでもいくつかの作曲家の作品はしっかりと心に残っています。バッハ、モーツァルト、そしていくつかのベートーヴェンのシンフォニー。私がそれらのクラシックの作品から最も強く感じるのは、光に包まれて祝福を受ける荘厳なイメージです。多くの苦悩を抱え、困難とともにありつつも、そこに至る厳粛なイメージです。現実の作曲家は、それぞれが厳しい人生を歩み、多くの苦悩を抱えていたのではないかと思います。でも、彼らから出てくるのは、少なくとも今でも残っているのは、その祝福に満ちた物語です。不思議でもあり、励まされる気もします。
2024年は家族3人とも「ああでもない」「こうでもない」と試行錯誤の一年でしたが、何とか皆健康で、それなりに無事に年を越せそうです。良かった、良かった。
それでは皆様また来年お会いしましょう。
来るべき2025年が皆様にとって幸多いものでありますように。
Bye Bye Blackbird!
And
Get Happy!
本当にどうでも良い話
読まれる方には全く無意味な情報であることは百も承知なのですが、月に一度はコラムを更新するようにと言われているので、どうかお許し下さい。
私は、大きなお風呂に入るのが昔から大好きです。
きっと風呂好きだった父の影響だと思うのですが、外で銭湯に入るのが昔から好きでした。休日の夕方(あるいは昼間でも)に家族で風呂に行って、ゆっくりと大きな風呂につかることは、私の小確幸(小さいけれど確かな幸せ)のひとつです。
妻も結構な風呂好きなので、結婚してから日常的に外で風呂に入ってきました。息子も「おむつ」が取れるかどうかといったころから、男湯に連れていって一緒に入っていました。結果、息子も風呂好きに育ち、「疲れたから風呂に行こう」と誘ってくる人間になりました。英才教育というやつですね。
ということで、昔から外風呂に入って楽しんできたのですが、最近は、入浴料の値上げが激しく、ちょっと躊躇する値段になってきました。最近は人も多いですね。サウナブームとやらで、昔は、おじさんの憩いの場だったサウナも、最近は若い人が目立ちます。サウナハットを被っている人を見かけた時には、「本当にいるんだ」とびっくりしました。
風呂でぼけっとしていると、周りの人たちの話し声がよく聞こえます。その中には、なかなかに興味深いものも混じっています。先日も、若い男の子が何人かで風呂の縁に腰掛けて熱心に話し込んでおり、「彼女じゃなくてもいいからさ、俺、女の子キープしたいんだよね」「ほんと、キープしたい」とか格好つけて話しており、「一体どういう状態を求めているのだろうか?」と思わず聞き耳を立ててしまいました。どうも良からぬことを思い描いているようでしたが、皆であれやこれやと真剣に検討しており、まさに傑作でした。
たまにそういう楽しい出来事があると、風呂を出てから、「実は、こんな話をしている人がいてさ…」と妻や息子に報告します。すると妻も息子も面白がって無意味に話題が膨らみます。「こういう状態を目指しているのではなかろうか(父)」とか「そうではなくて、実は、こういう状態なのではないか(母)」とか。あるいは、「きっと、最近、女の子の関係で痛い目に遭ったに違いない。そんなこと考えているから、キープできないんだ(父)」とか、「その考え方自体に問題があるので、痛い目に遭うんだ(母)」とか、「キープとか何とかより、そもそも周りに女の子がいないんだけど(息子)」とか。さらには、「やる気のある人間なら、それでも何とかするから、そんなことは言い訳にならない(父)」とか、「お父さんは、たまたま恵まれてただけだ(息子)」とか。コンビニで買ったアイスを皆で食べながら、ひとしきり検討してみたりして。全くもって余計なお世話ですが。
そんな外風呂なのですが、何といっても、一番気持ちが良いのは、長い距離を走ったり、長時間自転車に乗ったりして、ぐったりと疲れた体で入る風呂です。これは体がほどけそうになります。それと甲乙つけ難いのが、旅先での朝風呂です。出航直後のフェリーの風呂もまた堪らない。間違いなく小確幸のひとつです。
ああ、今回は、これまでで一番どうでも良い(ひどい)話を書いてしまった。
また仕事とは無関係の話
昨年、村上春樹の「街とその不確かな壁」を読みました。この本は2023年に刊行された本で、「世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド」(1985年)の続編という位置づけです。
「世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド」を最初に呼んだのは、大学生の時で、今でも最も好きな村上作品のひとつです。この本は、「世界の終わり」と「ハードボイルド・ワンダーランド」の2つの部分から成り立っています。2つの物語は交互に進行し、最後に両者の関係が解き明かされるという構造です。それぞれ示唆に富む内容になっており、とても考えさせられます(以下、ネタバレ多数です)。
「ハードボイルド・ワンダーランド」の主人公は、最終的に自ら望まない形でその意識を失うという運命に陥ります。ただ、それは決して不幸なものなのではなく、自ら構築した自己完結した意識世界に入り込むことを意味しており、ある意味では幸福なことでもあります。そこには激しい喜怒哀楽やエゴのもたらす苦しみはありません。しかし、主人公は、今のままの自分でありたいと痛切に感じます。「こんな人生でも、それを抱きしめて生き続けていたい」と煩悶するのです。年を取って多くの輝く可能性を失い、他人から見たらパッとしない人生であっても、それこそが自分の人生であり、そこには固有の喜びがあるので、それを大事に今後も生き続けたいと感じて苦しむのです。ここに描かれているのは私たち自身の問題でもあります。とても心に残ります。
「世界の終わり」の主人公は、先ほど述べた自己完結した意識世界で生活しており、平常心を得られる見返りに「影」と切り離され、次第に人間らしい感情を失いつつあります。それはある意味では幸福なことですが不自然なことでもあり、主人公は元の世界に戻るべきか否か悩みます。しかし、最終的に自意識の世界に留まることを選択します。それは、ある若い女性と一緒にいたいと強く感じてのことです。この女性も「影」と切り離されて心を失ってはいるものの、その片鱗なようなものがどこか感じられます。そして、主人公は特殊な仕事をする中で、その女性の心の断片を感じることになります。その温もりをかすかに感じ、彼女とともにありたいと強く願うのです。その時、ずっと忘れていた「音楽」が彼の口をつきます。それはダニー・ボーイの美しいメロディ-です。主人公の心は柔らかさを取り戻し、目からは涙が溢れます。ここを読む度に、僕はビル・エヴァンスの演奏する美しいダニー・ボーイの演奏を思い出し、グッときてしまいます。ここには人が人を求めるということの大切な意味(のうちのひとつ)が描かれているように感じられます。それもまた私たち自身の問題です。
「世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド」には、そのほかにも沢山の印象深いシーンが描かれています。それは滋養となって私の一部を形成し、心を豊かにしてくれているように感じています。
小説でも音楽でも良い作品に出会うと励まされます。
それは時を超え、場所も越えて我々に働きかけてきます。
どうしてそんなことができるんでしょうね。
他山の石
今回は少しだけ仕事に関係するお話を。
唐突ですが、我々の世界も随分と変わりました。私のころと比較すると、司法試験の合格者は倍以上になりました。一時は3倍近くになっていたこともあります。そこまで一気に人数が増えてしまうと、人があぶれてしまって、就職先に困ったり、資格は取れても仕事がなかったりといった人が出てきてしまいました。合格してもうま味が少ないということで、司法試験自体の人気も無くなってしまいました。
不祥事も以前より目に付くようになりました。宜しくない仕事をしている弁護士の存在を日常的に感じるようになり、「弁護士倫理」ということが頭をよぎる機会が増えました。情けない話ですが。世間の弁護士を見る目も厳しいものに変わってきました。
少し話は変わりますが、私のように田舎の弁護士会にいると、ある程度の経験を積むと、弁護士に対する苦情に携わることになります。
一番最初が副会長在任時の「市民窓口」対応です。弁護士会には、日々、弁護士に関する様々なクレームが持ち込まれるのですが、その初動対応をするのが副会長の仕事の1つになっています。面談してお話しを聞いたりして、しかるべき処理をしていきますが、なかなかに苦労の多い仕事です。ただ、そうした仕事をしていると、何が人々の不満や強い怒りを生んでいるのかが理解できるようになってきます。それは「横柄な態度」、「不誠実な連絡/対応(報告しない/電話に出ないなど)」といった事柄であることが多いようです。「弁護士だと思って、何様のつもりだ」とお怒りなのであって、社会人としてのきちんとしたマナーが弁護士にも求められているのです。当たり前のことですが、対応していて身の引き締まる思いがします。
それとは別に、弁護士に対する懲戒処分を求める申立(懲戒申立)が弁護士会になされることもあります。申立があると、まず「綱紀委員会」というところに案件が回されます。そこでまず調査・審議して、懲戒委員会の審査を求めるか決定します。私も数年前からその委員を仰せつかっています。内容にわたるお話しは勿論一切できませんが、ここでもなかなかストロングタイプの案件を扱っています。それなりの数を扱っていると、何がトラブルを生んでいるのか、避けなければならない事柄は何かといったことが段々と理解できるようになります。そして、不満を抱かれやすい弁護士というのが、実はある程度顔ぶれが決まっていることや、ある特定の個人的資質が人々の怒りを招いていることに気づかされることになります。身の引き締まる思いがします。
余談ながら(ここまで全て余談ですが)、我々の仕事は仕事それ自体から学ぶことの多い、いささか特殊な仕事でもあります。人々から話しを聞いていると、何がトラブルのもとになるか、それが経験的に手に取るように分かってくるからです。例えば、日常的に離婚案件を扱ううちに、「ここが奥さんの怒りポイントだな」とか肌身に染みて理解できるようになります。同じミスでも、これは致命的だなとか分かってきます。
そうしたいろんな場面で、「他山の石」という言葉が頭に浮かびます。
油断していると明日は我が身だぞと耳元でささやく声が聞こえます。
こんなこと書いてどうするんだ。
夏の思い出
50数年も生きてくると、季節毎に色んな思い出が出来ますね。読まれる方には全く無意味と承知してはいるのですが、ほかに書くことも思いつかないので、ご容赦下さい。
暑い盛り、「盛夏」ということで最初に思い出すのは、何といっても司法試験の受験時代です。一番暑い時期に最も困難な論文試験がありました。私は京都会場で受験していましたが、京大は暑かった(同志社は涼しかった)。皆すごく気合いが入っていて、気圧される感じでした。あのころは実によく勉強した。
次に思い出すのは、実務に出て1年目の夏で、当時は神戸地検の刑事部にいました。社会人1年目は皆同じだと思うのですが、私も慣れない仕事が辛くて、毎日逃げ出したい思いでした。周囲にも恵まれて何とか乗り切りましたが、いや~辛かった。
その次というと検事を辞めた年の夏でしょうか。挫折感もあってなかなかに辛い暑い夏でした。ただ、とりあえず行き先はあったので、そんなに焦らず、のんびり暮らしていました。毎日夕方になると妻とぶらぶら散歩に行ったり、エアポケットのような時期でした。お金の心配はありましたが、今思うと悪くなかった。まだ夫婦二人で若かったですし。
弁護士になり、特に子どもが生まれてからは、妻の母方の実家の大分に毎年帰省(旅行)していたのが夏の一番の思い出です。私は両親とも大阪の出で、いわゆる「田舎」というもののない人間なので、とても新鮮な経験でした。夏休みの開放感も手伝って、そこには何とも言えない喜びがあったように思います。そのころは妻の祖母がまだ存命で、息子を「ひいばあちゃん」に年に1度会わせる良い機会であり、息子にとっても人生の宝になったと思います。今でも九州と聞くだけで、郷愁のようなものを感じるくらいです。
そんな風にして、夏には辛い思い出や楽しい思い出が沢山ありますが、後で振り返った時、今年(2024年)の夏はどんな風に感じるんでしょうね。いまのところ、今年の夏は一生懸命自転車に乗って大汗を流しており、家族旅行では初めて岩手県に行きました。中尊寺が立派なことや、盛岡が思っていたよりも遙かに都会であることに驚きました(残念ながらレコードの出物はありませんでしたが)。遠野も雰囲気があってなかなか良かった。まあ平凡な日々ではありますが、それなりに良い思い出になっていそうな気がしています。でも、平凡と思える日々を過ごせることが、やっぱり一番ですよね。
年齢を重ねて感じること。
当然のことですが、生きていると否応なく年を取り、年を取るにしたがって様々な物事が変化します。細かい字が見えづらくなり、太りやすく痩せにくい体質になります。
ただ、それなりに悪くない面もあります。
ひとつは、経験を積むことで、若いころよりも色んなことが実感をもって理解できるようになります。「人の気持ちが分かる」ようになります。それは、私のような職業にとっては望ましいことです。もちろん価値観も変わってきます。色々な経験をし、多様な価値観と出会い、絶え間なく影響を受けて、独りよがりで硬直気味な価値観は、試練を受けて修正を余儀なくされます。それに伴って自分に対する認識や評価も変化し、現実の自分に適合したものへと変容を遂げていきます。そして、精神的にはタフになり、若いころほど簡単にへこたれなくなります。「あつかましく」なり、文句も言えるようになります。
きっと皆さん似たり寄ったりではないでしょうか。
年を取ってきて、率直に思うことは、年長者(おじいさん、おばあさん)はすごいなということです。若い頃は、当たり前に年をとり、歳月の経過によって年長者になるだけで、別に大したこととも思っていませんでした(不遜ですね)。ただ、年を取ること自体が決して容易なことではないと身に染みて分かってくると、年を取るということ、それ自体がひとつの達成のように感じられてきます。
昔は杖をついたり手押し車を押して歩いている年配の方を見かけても、ネガティブな印象しか受けませんでしたが、自分の親が年を取り体が不自由になって自由に出歩くことができなくなると、そうして自力で動くことがてきるというだけで、それはとても素晴らしい、有り難いことであって、祝福すべきことであると感じられるようになりました。
意識していても、意識していなくても、どんどん自分の立ち位置が変わっていく。「こっち」にいるつもりが、いつの間にか「あっち」にスライドしていく。
当たり前ですが、初めての経験で、何とも不思議な感じのするものです。
少しは賢くなっていればよいのですが。
等身大と言えば聞こえは良いですが。
ここ数年父親に譲ってもらった1300ccの小型車に乗っています。それまでに乗っていた車が突然故障し、半導体不足で新車も手に入らなかったので、やむなく免許を返納する予定になっていた父親の車を譲り受けました。仕事柄、人目が気になって少し気恥ずかしい思いをすることはありますが(みんな実に良い車に乗っていますね)、実用という面では何の不足もありません。燃費も良いし、基本一人で乗っているので、これで必要にして十分です。父親が買った最後の車になるので、その分最後まで大切に乗ってやろうと思っています。そろそろ初年度登録から10年くらいですが、車とお互いに労りあいつつ、ボチボチやっていこうと思っています。
物を長く大切に使うと言えば聞こえは良いですが、どうも私は貧乏性なようで、自分のためにお金を使うのが下手くそです。趣味の物を買い換えるのもとても時間がかかります。
そんな私ではありますが、この度、前々から欲しかったさる有名なメーカーのカーボンのロードバイクを手に入れました。中古ではありますが、年式もとても新しく、ほぼ未使用と言って差し支えない状態の良いものが、かなりリーズナブルな価格で見つかったので、思い切って購入しました。ということで、現在、喜びをかみしめつつ乗っています。でも、買い換えるのに結局8年もかかりました。
そういえば、スピーカーも買い換えるのに10年以上かかりました。今使っているスピーカーもエントリーグレードに近いクラスのものですが、「悪くないな」と自己満足に浸りつつ日々楽しんでいます。ただ、何時かは30㎝以上のウーファーのJBLを手に入れたい、それなりの音量でジャズが聴きたいというのが、私のささやかな野望です。先日、東京出張の際、さる有名なジャズ喫茶でJBLのスピーカーで大音量のジャズを聴きましたが、実に堪えられませんでした。あそこまで無理なのは当然としても、もう少し良い音で聴きたい。でもそうなると、スピーカーに合わせてアンプもプレーヤーも相応の物に買い換える必要が出てくる。そんなことをしているうちに沼に嵌まる。困った(困ってない)。
ここまで書いてきて何ですが、我ながら実に小市民的ですね。世の人が「弁護士」に抱くイメージとは相当かけ離れている気がする。
そう言えば、昔「何時かはクラウン」とかいうキャッチコピーがありましたね。まあ私には関係ないですが。多分。知らんけど。
 東近江で離婚・相続・賠償・借金の法律相談なら
東近江で離婚・相続・賠償・借金の法律相談なら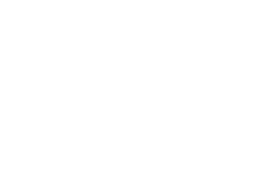 ご予約・お問い合わせ
ご予約・お問い合わせ