法律コラム
最初は知らないことばかり。
我我弁護士も、最初は知らないことばかりです。でも、色々と事件を手がけ、その中で経験を積んで成長していきます。ひとりの家庭人・社会人として人生経験を積み重ねます。それは、他の仕事と同じです。
確かに、我我の仕事はいささか特殊ですし、それなりに法律の勉強はして司法試験には合格しています。ただ、司法試験の受験科目は、法律全体から見ればほんの一握りのものに過ぎません。社会には膨大な法律があり、実際の事件を処理するには、そうした法律の理解が必要になります。また、対象となる法律が、裁判の場で、あるいは、実際の社会でどのように解釈され運用されているのかという理解も必要不可欠です。そこも試験に合格した段階では、ほとんど身についていません。専門であるはずの「法律」という分野でさえ、最初はこんな状態です。
「社会経験」や「社会常識」という面でも、最初は足りないことばかりです。特に私のように大学を卒業してすぐに法曹の世界に入ってしまった場合はなおのことです。「対人関係」についても同様のことが言えます(ここが最も困難ですが)。年配の相談者さんや依頼者さんから見れば、自分の息子や娘くらいの、ちょっと法律に詳しいだけの社会常識にいささか欠けた人間というように見えているのではないかと思います。その認識に誤りはないと思います。
そんな状態で、「裁判官」や「検事」「弁護士」になるわけですので、考えてみればかなり怖いことです。それでも裁判官や検事は、経験豊富な先輩の指導をこってりと受け、組織的に鍛えられるのでまだマシですが、我我弁護士は様々です。正直ビクビクものであり、「弁護過誤保険が心の支えだ」と豪語している先輩弁護士もおられました(今では立派な先生になっておられます)。
でも、実務に出たら一人前です。「知りません」では済まされませんし、失敗は基本的に許されません。そこで、我我は、現場に出てから必死になって調べることになります。その都度、その都度、必要な法律等の法規を調べ、関連する実社会の手続きを調べ、どう物事を進めるべきなのか考えます。専門家(他の士業の先生方)に意見を求めたり、依頼者さんに業界ルールや事件処理に必要な周辺知識をみっちりと教えて頂きます。そうして、できるだけ怖い目に遭わないようにと必死に頭を働かせるのですが、それでも時には失敗し、痛い目に遭います。すると今度は、それが致命的な失敗にならないようにと、また必死に頭を働かせます。
きりがないと言えばきりがありませんが、このようなトライ・アンド・エラーを積み重ねて、我我弁護士は少しずつ法律家として成長していきます。
また、研修を通じて専門的な知識を蓄えることもあります。弁護士の中には、特定の分野を興味を持って熱心に掘り下げ、希少な経験を積んで、その道の専門家といった力をつける方があります。そうして、その知識・経験を、日本弁護士連合会の会員向け講義を通して、我我一般の弁護士に分け与えて下さいます。地方で仕事をしている私などは、オンラインでそうした講義を受け、必要な知識を蓄えています。
そうして、最初は何も知らないところから、少しずつ成長していくわけです。私も少しは頼りになる弁護士に成長できていればよいのですが。
これって「法律」コラムなの?
「法律コラム」と銘打ちながら、ここのところ、ほぼ仕事(法律)の話は書いていません。身辺雑記というか、個人的な思いというか、そんなことばかりです。ネット上にゴマンとある情報を今さら私が書いてもなという思いもして、仕事のことをあまり書かなくなりました。
そんなことより、もっと違うことを書いた方が皆さんの参考になるのではと思って、自分自身という人間について書くようになりました。
このHP(ホームページ)を作るとき、自分に困り事があって弁護士を探すとしたら、どんな情報が知りたいかと考えました。その時気になったのは、相手の人間性というか、どんな考え方の人なのかということでした。ただ、どのHPを見ても、とても頼りになりそうな立派なことが書いてあるのですが、そのあたり(人間性みたいなもの)を推し量るのはちょっと難しそうでした。そこで、その一助になればと、こんなコラムを書くようになりました。最近の流れですと、SNSを活用してそうしたことをするべきなのでしょうが、個人的にSNSにはいささか及び腰なので、HPのコラムを使うことにしました。あくまでHPの一部で、ネガティブなことにはほぼ触れませんので、実物よりかなり立派になってはいると思いますが、私がどんな人間かその片鱗くらいはうかがえるのではと思っています。
正直に言うと、こんなコラムを書くのにはもうひとつ、いささか自己弁護じみた理由があります。今の世の中、他者を評価・批判することに熱心で、私も匿名で色々な批判を頂きます。反省すべき点も少なくありませんが、その中には「ちょっとそれはないんじゃないか」と感じるものもあります。ただ、そうした批判に一々反論しても、ほとんど無意味というか不毛ではないかと思いますし、それよりは能動的な形で自分について情報を発信する方がより有益に思われます。それでこんなコラムを書いています。
とは言え、平凡に暮らしていて特に珍しい体験をすることもなく、特段深く考えて日々を過ごしているわけでもないため、あまり書くネタを思いつきません。そもそも、わざわざ読んで下さる方が本当に居るのかという不安もあります。
できれば月イチの頻度で、ボチボチと続けていければと考えています。また、折に触れて仕事のことも書いていきたいと思いますので、お付き合い頂ければ幸いです。
体を動かすこと
40歳を過ぎてから結構一生懸命運動をするようになりました。それまで運動とは無縁な生活で、若い時からそんなに積極的に体を動かす方でもありませんでした。そんな人間が、どうして体を動かすようになったかと言えば、理由は割と単純で、検診で「メタボ」と言われたことがきっかけでした。
ちょうどその頃、知り合いのK先生が、毎朝散歩したら随分痩せたとおっしゃているのを聞いて、私はマネをすることにしました。出勤前に毎朝30分くらいアクティブウォーキングをするようになりました。そして少しずつ間にランニングを挟むようして、走る距離も少しずつ伸ばしていきました。そして、最終的には20㎞くらいまでなら無理なく走れるようになりました。嬉しくて、毎日毎日、走り続けました。多い時は月に300㎞ほど走っていました(家族に呆れられました)。でも、さすがに数年して徐々に飽きてきました。
そこで、ランニングからロードバイク(自転車)に徐々に切り替えていきました。ロードバイクは一生懸命に乗ると、ランニングと変わらないくらいの運動量になります。ランニングとは比較にならないほど遠くに行くこともでき、旅行気分も味わえます。機材スポーツなのでギアをいじる楽しみもあります。ギアにこだわりさえしなければ、そんなに出費が嵩むこともありません。それからは暑い日も寒い日も関係なく乗り続けました。多い時で月に1000㎞以上、「気合いだ」と言って氷点下の寒い朝でも乗り続けました(家族に呆れられました)。
こうした執拗な運動のおかげで体重もそこそこ落ちましたが、何より良かったのは、体質が変わって体調を崩すことがめっきり少なくなったことでした。睡眠の質も上がったように思いますし、少し前向きになったようにも感じています。
ただ、そろそろロードバイク熱も冷めてきています。どうも数年で飽きるタイプのようです。このまま続けるにしても、何か新しい刺激なり工夫なりが必要そうです。
どうしようか迷っているのですが、妻は「黙々と一人でやるのが向いているようなので、次は水泳が怪しいのではないか」との意見です。でも水泳は昔から苦手だし、わざわざプールに行くのも面倒だし、ちょっと気が進みません。バドミントンをまたやりたい気もあるのですが、相手のあるスポーツなので、どこかのグループに入らないとできませんし、わざわざ体育館に行く必要もあるので、いかにも面倒です。でも何もしないと太る一方だし、これからは筋力も落ちる一方だし、どうしたものか…。でも、もし水泳に手を出したら、トライアスロンが出来るようになりますね(しないけど)。
月並みですが。
この春、息子が大学生になりました。
彼は1年浪人して、現役のころからずっと憧れていた大学に入りました。
この1年、彼は不安によく耐えて、現役のころとは比較にならない努力を見せ、そして結果を掴み取りました。大変な喜びようでした。
そんな彼を見ていて、僕は、自分のことを思い出しました。司法試験を受験していたころ、どんなに不安で苦しんでいたか、どうやってその不安と付き合いつつ努力したか、そして、それが報われたとき自分がどれだけ大きな喜びを感じたか。まざまざと思い出しました。
今回の件に限らず、彼を見ていると、自分のことを思い起こします(きっと親は皆そうですね)。高校に入ったとき、大学に入ったとき、自分が何を感じ、どんな気持ちであったかということ。世界が広がり、見える風景が変わり、空気の色さえ明るくなったような開放感を味わっていたこと。今から新しい何かが始まるのだという期待と不安。大人になっていく責任感。
今、彼がそうした風景を見て、新たな世界に足を踏み入れようとしているのだと思うと、ちょっと羨ましい気がします。
何はともあれ、あの小さくて僕と妻に頼り切りだった彼が、ここまで成長した。
いささかアンバランスではあるけれど、一人前なことも口にするようになった。
自分の弱さを自覚し、自分なりの強さも身につけつつある。
そして、これからは僕の見たことのない世界を見て、自分の力で人生を切り開こうとしている。
もちろん上手くいくかどうか分かりません。
色々と苦労するのは間違いのないところでしょう。
では、どうやってそれと向き合って乗り越えていくか。
もし乗り越えられなければ、どうやってそれを受け容れて自らの糧としていくか。
僕と妻はこれからそれを目にすることになります。
月並みですが、それを見るのが親として楽しみです。
ありがたいことですね。
ちゃんと役目を果たすこと
先日、妻が「Sさんの夢を見た」「どれだけ心の支えにしていたんだか」といったような話をしていました。
Sさんは、数年前に亡くなってしまわれましたが、その直前まで20数年もの長い間、某FM局でDJをされていた方で、その傍ら大学で英語の教員もされていました。バリトンボイスのすてきな声をお持ちの方で、亡くなられたとき、まだ60代前半でした。
Sさんは結構ご自分の考えをおっしゃる方で、社会や人生に対する思いを、時事ネタを絡めながらよくお話しされていました。正直、いささか教科書的過ぎるのではと感じる部分もなくはありませんでしたが、同感だと思うことも多く、とても良識的で信頼の置けそうな方のように感じていました。英語のコーナーが名物で、語学というものの奥深さの一端を味わうことができることから、私は毎日それを楽しみに聴いていました。また、ジャズがお好きで、よく古いスタンダードナンバーをかけておられたことも、私にとっては嬉しいことのひとつでした。
長らく朝の番組をやっておられた関係で、私はSさんのことを随分前から知っていました。特に車通勤をするようになってからは毎日のように番組を耳にしていたので、見ず知らずの他人なのに、Sさんのことを、まるで親戚か何かのように感じていました。Sさんが朝の番組をしていてくださることで、私は「ああ、ここにちゃんとした人がいる」「こういう人がいてくれて、社会はきちんと回っているんだ」という安心感を得ることができました。
それなのに、ある日突然体調不良とのことでお休みに入ってしまわれ、程なくしてお亡くなりになったというアナウンスがありました。余りに唐突だったので気持ちの整理がつかず混乱し、とても大きなショックを受けました。
Sさんの死は私にいくつかの教訓らしきものを遺していきました。
そのひとつは、人は与えられた守備位置にきちんと就き、そこでできるだけ前向きに努めを果たすべきだということでした。できるだけ言い訳せずに黙々と。
もうひとつは、当たり前のことではあるのですが、自分に対しても他人に対してもできるだけ誠実に努めるべきだということでした。多様な意見がありうる事柄について発言する際には、それが個人的な意見であると断ったうえで、決して物事を決めつけたり、自分の意見を押しつけたりしないこと。
そして何より、自分が辛くても、それを要らぬ人にまで伝えて無用に心配させたりしないこと。その強さを身につけること。
Sさんの生き方は、私にとって、ひとつのモデルケースとなり手本となりました。私は、自分が何かつらいときに、ふとSさんのことを思い出します。そして自分を鼓舞します。
Sさんが亡くなられた年、その年にあった最も悲しかったことのひとつとして、妻はSさんの死を挙げました。全くもって同感でした。似たもの夫婦ですね。
幸せな光景
大きな自転車の前と後ろに大きな子乗せをつけて四苦八苦しているお母さん。小さなお子さんを周りにウロチョロさせながら、ベビーカーを押しているお母さん。実際のお母さんの心中はさておき、「きっとお母さんにとって最も幸福な時期のひとつに違いない」と勝手に考えています。
仕事柄、離婚は身近で、色々な夫婦のパターンを見てきました。
世の中には、人格的に何か欠けているから離婚することになったんだという方もおられます。しかし、経験的に見る限り、婚姻関係の継続と人格の優劣とは直接的な(あるいは必然的な)関連性はなさそうです。不完全な人間同士の1対1の関係ですので、上手くいかないことも多々あって当然という気がします。合わないなら別れればいいというのも割り切った考え方ですが、その間に子どもがいる場合には、そう簡単にいかないこともあります。
余程のことがない限り、離婚や親権という選択それ自体に関して、私から率先して意見を申し上げることはありません。
ただ、例外というか、思わず口を挟んでしまうパターンがいくつかあります。ひとつは、お母さんがお子さんのことを手放そうとされているパターンです。滅多にないパターンですが、余程のことがあっての決断なのは明らかなので、本当は口を挟むべきではないと思いますが、思わず口を挟んでしまいます。もうひとつが、「ふた親揃っていたほうが子どものためだから」とお母さんが離婚を躊躇っておられるパターンです。でも、それだけなら私も口を挟んだりはしません。思わず口出ししてしまうのは、私から見ると酷い扱いを受けているにもかかわらず、子どものためと考えてお母さんが(無理に)離婚を思いとどまろうとしている場合です。そうした場合、私は「これは弁護士としてではなく、あくまで個人的な意見として申し上げるのですが…」と前置きをしたうえで、「必ずしも、そうした考え方に縛られる必要はないのではないか」ということを申し上げます。確かに、お子さんは片親で辛い思いをすることもあるかも知れないけれど、きちんと大切に育ててあげれば、そのことはきちんとお子さんには伝わるし、その方が不仲な両親のもとで育つより、かえって幸せなこともあるのではないかとお話しします。そう思うには私なりに理由があります。ときに離婚したお母さんが何か別に困りごとがあって相談に来られることがあります。そして、その際、ちょっと大きくなった(でも成人前の)男の子や女の子が、お母さんの応援団みたいな感じでくっついて来て、横から「そんなこと言ってたらアカン」「こうした方が良いって」みたいに熱心にサポートすることがあります。お母さんも何のかんの言ってもお子さんを頼りにしている様子が見て取れます。そんな光景を目にすると、「ああ、このお母さんは、お子さんを大切に育ててこられたんだな」と思います。それが分かっているから、お子さんもお母さんのことを大事に思って(「頼りないし、自分が助けなければ」と思って)ついて来て色々と口出しするのだろうと思います。そんな光景も見ているので思わず口出ししてしまうわけです。
小さなお子さん連れのお母さんを見て、その近くにお父さんらしき人の姿がないと、「仕事なのかな」と思ったり、「離婚してシングルなのかも」と思ったりします。あるいは、最初から一人で育てようと思って出産されたのかも知れません。そのいずれであっても幸せな光景に違いはありません。いずれにせよお子さんがすくすく育つと良いなと思います。他人事なのに不思議なものですね。
普段は意識しないけど大切なこと
コロナになって数年経ちます。最初のころは、それまで「当たり前」に感じていたことが、もろくも崩れてしまった思いがして、何とも言えない気持ちになりました。
ある意味で意外だったのは、そんな状況で自分が最も強く求めたものが「音楽」や「絵画」や「本」であったということでした。もっと、現実的に役に立つ何かではなくて。それらに特に造形が深いわけでもないのに。そして、何よりも嬉しかったのは、そう感じているのが自分だけではなく、社会の多くの人が同じように感じているようだという事実でした。
そんな気持ちを抱えて、私は、時間があったらまとめて聴きたいと思っていたミュージシャンのCDを買い集めて系統立てて聴いたり、少しずつ営業を再開した都市部のレコードショップに足を運んでは気になっていたアナログ・レコードを買い集めてじっくり聴いたりするようになりました。以前よりも少し丁寧に音楽と接するようになりました。
ときに、「文系はすぐ役に立たない。即戦力にならない。理系の重要性をきちんと認識して、そちらに予算を回すべきだ」というような社会の声が聞こえてくることがあります。そのような議論の場における「文系」や「理系」という言葉が一体何を指しているか、正直、よく分からないところはありますが、そういった意見を聞く度に、「いや、そんな単純なことではないはずだ」と私は感じてきました。「単純な利便性の問題に還元できないからこそ、そこには本当に重要な何かが含まれているはずだ」「そこから学べること(得られること)の重要性において、決して、理系に引けをとらないはずだ」と反発する気持ちがありました。そして、コロナを経験した今、その思いはより強くなったように感じています。
以前、村上春樹さんが何かのエッセイで「自分は、物語を作ることで、暗い森の中で(邪悪な何かと)闘っているんだ」というようなことを書かれていました。それを読んだとき、私は、その文脈もあって、独善的で排他的なもの、単純であるが故にとても力強くて攻撃的なもの、そうしたものに対抗できるイメージを持てるように、村上さんは物語という枠組みを使って我々読者に働きかけているのだと理解しました。私はそのとき「正にその通りだ」と思いました。それも物語の持つ重要なひとつの側面なのだと。
読書にせよ、音楽鑑賞にせよ、美術鑑賞にせよ、それらは簡単に言葉では説明のできない大切な体験をさせてくれます。それは何かと比較して単純に優劣を論ずることの難しい事柄であるように感じられます。ただ何となく分かるのは、それが自分にとってとても重要なものであり、コロナのような状況に陥ったとき、自分を助けてくれる何かなのだということです。生きる滋養となる何かと言えばよいのかも知れません。
そうしたものであるからこそ、困難な状況となって人々はそれを求めたのでしょうし、人は営々と物語を紡ぎ、音楽を奏でてきたのではないでしょうか。
「悪い人なのに何故弁護するんですか?」
たまに聞かれることのある質問です。「きっと、お金のためなんでしょ」というところで、何となく皆さん納得されているのではないでしょうか。でも、本当はそうしたことではないと思います。現在の刑事事件の報酬は決して高額なものではありません。
では、何故、弁護士は、お金のためでもないのに、皆からある意味では蔑まれるような仕事(「悪い人」の弁護)をするのか?
私の理解では、そうなっているのは過去の反省によるものであり歴史の産物です。
過去には、捜査する人間(時に裁判官)が色々と調べて「こいつは悪い奴に違いない」と判断し、いわば正義感のようなものも手伝って拷問のようなことまでして白黒つけていく、それが正当化されるという時代がありました。そこには「どうせこいつの言っていることは嘘だろうから相手にしない」とか「こんな奴には味方はいらない」といった態度も見受けられました。そうして言い分もきちんと聞かずに(無理矢理)自白させて、それを根拠に今度は有罪にしてしまうといった事例も後を絶たず、その結果として、無罪の人が誤って有罪になってしまうという悲劇も起きました。そんなやり方には眉をひそめる人も相当数いました。そうした態度が最も顕著だったのが第二次大戦中ではなかったかと思われます。
それで戦後、その反省も踏まえて、疑われている側の人も、きちんと自分の言い分を言うことができるようにしよう、そのうえで、公正なルールに則って判断するようにしようということになりました。その方が、最終的に出てくる結論も説得力が増して、制度としても信頼されるだろうということもありました。そうして、誤判をできる限り防いで、刑事事件処理の制度としての信頼性も担保するため、その最も効果的な方策のひとつとして、もしかしたら「悪い人」かも知れないが、そのサポートのために弁護士を付けようということになりました。弁護士を付けて、言い分もきちんと言えるようにしよう、きちんと決められたルールが守られているかチェックしよう、そのようにして社会に信頼される公正な裁判を実現しようということになりました。それで「悪い人」にも弁護士が付くことになったわけです。
その意味では、弁護士は、本来的にとても損な役割を引き受けさせられたと言えるかも知れません。「無実の人を救う」という側面を除けば、とてもわかりにくい立場であり、周囲の理解を得ることは容易ではありません。ときに「お金目当て」という非難まで受けかねません。
しかも、現実の事件はきれい事では済みません。そこには様々な苦労があります。被疑者・被告人の中には、対応が非常に困難な人もいますし、無茶を言う人もいます。そのため口論になったり、身の危険を感じることもあります。そういう意味では割に合いません。
では、弁護士は嫌々やっているのかと言えば、私はそうではないと思います。多くの弁護士は、自分たちがきちんと適切に役割を果たすことで、無罪の人が有罪にならずに済んでいるのだ、そして、この民主的な社会の基盤が適切に保たれているのだという思いで、大きなやり甲斐をもって、その役目を果たしているように見受けられます。
弁護士は、他の立場では出来ない重要な形で社会に貢献している思いで「悪い人」の弁護をしているのです。
それって、すごく価値のあることだと思いませんか?
これが、上記のご質問に対する私なりの回答です。
音楽はお好きですか?
今回は仕事を離れて趣味の話を。
タイトルからしてバレバレですが、私は音楽を聴くことがとても好きです。
若いころは、その時々の流行りのものを聴いていましたが、30歳を過ぎたころからJAZZを熱心に聴くようになりました。きっかけは割とはっきりしていて、村上春樹さんが書かれた「Portrait In Jazz」という本です。この本は和田誠さんの挿絵(ミュージシャンのポートレイト)に村上さんが、そのミュージシャンにまつわる文書を添えるといった趣向のもので、最初に読んだのはまだ結婚する前でした。それから何度も繰り返し読んで、私は「音楽を聴くということは、こんなにいろんな感情を味わうことのできることなんだ」という新鮮な驚きを感じました。その片鱗でも味わいたいと思うようになりました。それである時意を決してガイドブックを手ががりに、手当たり次第にJAZZのCDを買い漁っては聴くようになりました。
不慣れなジャンルの音楽なので、最初は全く良さが分かりませんでした。一体、何をしているのか、どこがすばらしいのか、最初はほとんど何も理解できませんでした。でも、しつこく聞き続けるうち、少しずつその魅力が分かるようになっていきました。そして気がつくと夢中になっていました。
ただ、村上さんが感じておられるほどには、鮮やかな感動を味わったり、多くのことを感じたりすることは、(まだ)できずにいます。それは、感受性や鑑賞力の問題であって、それだけものが自分には(少なくとも現時点では)備わっていないのだと理解しています。
それでも、JAZZを一生懸命聴くようになって、それまでとは異なる気持ちを味わうことができるようになり、それによって人生が豊かになったと感じています。単純に、格好良いなとか、すごく綺麗だなとか、気持ちよく演奏してるなとか、分かりやすい印象を抱くこともあれば、ときに言葉では上手く説明できない思いになることもあります。それは、あえて言うなら、困難ではあるが前向きに頑張ろうというような励ましのようなものであったり、「それで良いのだ」という他者からの承認(による安堵)のようなものです。歌詞があれば言葉に託していけるのですが、JAZZはボーカル抜きの器楽のものが多いのに、それでも実に色んなことを感じさせてくれます。ときに感情を揺さぶられます。すごいことだなと思います。
また、そうした体験を通じて、私は、簡単に評価を決めてしまわないことの大切さにも改めて気づかされました。そして、何かを評価することは、同時に、自らの力量をもあからさまにしてしまうことなのだということも。「こんなもの、つまらない」「あんな考え方はくだらない」と言うことは、もしかしたら、そのすばらしさや妥当性を理解できるだけの素養や能力を欠くことを、対外的に露呈しているに過ぎないのかも知れない。
JAZZが好きになると音楽全般に敬意や興味を抱くようになり、結構いろんなジャンルの音楽を聴いてみましたが、何故かJAZZほど夢中になれずにいます。きっと相性があるんですね。
法律相談の注意点
今回は「法律相談」についての、ちょっとした注意点をお話ししようと思います。今回は箇条書きで行きます。
(1)ご自分や相手さんの名前等は、予約の際に正直に教えて下さい。
弁護士は、以前にご相談を受けた方を相手方とするような相談には応じられないという職業倫理があります。例えば、ご夫婦が離婚問題で揉めているとして、夫から相談を受けた弁護士は、たとえ依頼を受けなかったとしても、後日、その妻から相談を受けることはできません。ですので、予約のご連絡を頂いた際、弁護士は、ご自身と、紛争の相手方のお名前等をきちんと確認しなければなりません。ただ、たまに「相談するまで言いたくない」という方がおられて、ちょっと困ってしまいます。守秘義務があるので、お聞きしたことは他には漏らしません。予約の際には、ご自分や相手さんの名前等をきちんと正直に教えて下さい。
(2)相談前に相談内容を頭の中で整理してきて下さい(可能なら箇条書きでも良いので文書にまとめて整理してみて下さい)。
迷って弁護士に相談しようと思われる案件ですので、その内容は込み入ったものが少なくありません。複雑過ぎてご自分でも、なかなか上手く理解できていないこともあります。ただ、その状態のままで相談に来られますと、ご自身でもどこからどう話してよいか分からず混乱してしまい、当然、聞いている我々もお話しのポイントが理解しづらくて、なかなか相談がスムーズに進みません。限られた相談時間が無駄になってしまいます。ですので、できれば事前にご自身の頭の中で事実関係や問題点を整理して来て下さい。簡単にでも良いので、書面にまとめられればよりベターです。それによってご自身の中でも整理ができますし、相談も中身の濃いものにできます。なお、目の前の弁護士は、あなたや、あなたの悩まれている件について、まっさらで、全然何も知らないのだということを、くれぐれも忘れないようにして下さい。たまに前提をすっ飛ばしてお話しになる方がおられますので。
(3)事前にお調べになった情報にとらわれないで下さい。
インターネットが発達した結果、「こんなものまで」という情報が得られるようになりました。几帳面に綿密に下調べをして相談に来られる方がありますが、事前にお調べになった情報にとらわれるあまりに、こちらの話をなかなか信用して頂けないという矛盾した状態も生じています。「先生はそんなことを言うが、○○にはこう書いてあった」「○○だけでなく、△△にもそう書いてあった」といったような類いのことです。ただ、インターネットの情報は、内容が不正確なものが少なくありません。ある意味「嘘ではない」ものの、とても例外的なケースを、あたかも原則であるかのような書き方をして、読んでいる方にあらぬ誤解(期待)を抱かせるものもあります。実現可能性の低いものを、あたかも実現できるかのように誤解を与えるものもあります。法律事務所のホームページも例外ではありません。そうした事前の情報と比べると、目の前の弁護士は、正にあなたのケースについて、あなた自身から直接事情を伺って、いわばオーダーメイドでアドバイスをしています。経験等も付加したアドバイスをしています。そもそも力量が備わっていないのは論外ですが、少なくとも、そうでないようなら、目の前の弁護士の話に率直に耳を傾けても決して損はないと思います。
 東近江で離婚・相続・賠償・借金の法律相談なら
東近江で離婚・相続・賠償・借金の法律相談なら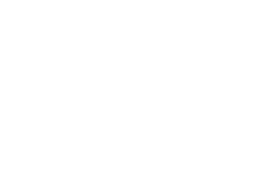 ご予約・お問い合わせ
ご予約・お問い合わせ